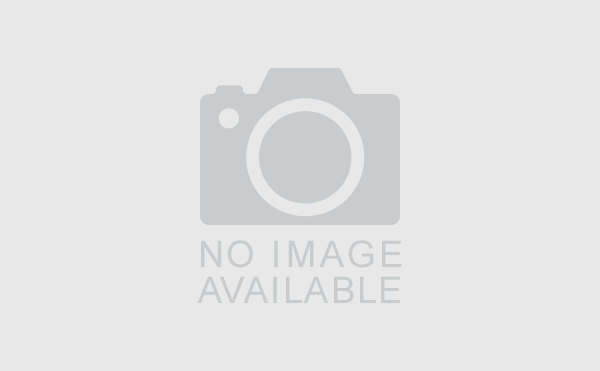2025年10月1日施行の改正育児介護休業法
はじめに
2025年度は、4月1日と10月1日の2段階に分けて育児介護休業法が改正されます。
その都度、法改正に対応する会社もあれば、4月1日時点で10月1日改正も踏まえて対応済みの会社も見受けられます。
個人的には、今回の改正で最も難易度が高いのが、10月1日施行の「柔軟な働き方を実現するための措置等」だと見ています。
今回は、おさらいも含めてポイントを見ていきたいと思います。
柔軟な働き方を実現するための措置等とは
簡潔に述べると次のような制度です。
会社・・・以下の5つの中から2つ以上の措置を制度として設ける。
① 始業時刻等の変更
② テレワーク等(1箇月あたり10日以上)
③ 保育施設の設置運営等
④ 養育両立支援休暇の付与(無給可、1年あたり10日以上)
⑤ 短時間勤務制度
従業員・・会社が上記の中から設けた制度のうち、1つを選択して利用できる。
(ここでいう「従業員」は、3歳から小学校就学前の子を養育する者をいいます)
4月1日改正は主に適用範囲の拡大だったものが、10月1日改正のこの措置はまったくの新設というのが難易度が高い理由です。
①から⑤を単体で見れば既に導入している会社もあります。
しかし、これらを複合して1つの制度として運用することによって、従前には想定できなかったトラブルの発生が十分に考えられます。
本措置のポイント
1:①から④の措置は、基本的にフルタイム勤務を想定していること。
意外と見落とされていますが、制度設計上とても重要なポイントになります。
2:①から⑤の措置は、1つを選択して利用できればいいこと。
多くの会社では、申し出のあった1つの制度だけを適用する運用を想定していると思います。
しかし、就業規則の規定(表現)次第で「併用可能」と解釈されるおそれもあります。
このようなことがないように就業規則や社内書式を作りこむことが肝要です。
3:従業員が期間内に制度の変更を希望した場合にどうするか。
このようなケースは十分に想定されます。
3歳以降の意向確認は「適切な時期に」となっているため、この時期設定も重要です。
従業員の意向だけでなく、その他従業員や事業運営の観点からも運用を想定しておくといいでしょう。
4:養育両立支援休暇の取得理由。
この休暇について厚生労働省のQ&Aでは、「就業しつつ子を養育するのに資するものであれば、いかなる目的に利用するかは労働者に委ねられることとなります。」とあります。
利用例としては、「例えば、通常保育所に子を迎えに行く配偶者が出張等で当該迎えができない日に時間単位で休暇を取得し保育所に子を迎えにいく、子が就学する小学校等の下見にいくなど。」とありますが、養育に資さないケースもあり得ると思います。
また、会社の努力義務である育児目的休暇を既に導入している場合は、育児目的休暇の制度も確認しておく必要があります。
おわりに
このように「柔軟な働き方を実現するための措置等」には多角的な視点から検討をしなければなりません。
制度として設けなければならない以上、就業規則の精度がトラブル予防に直結します。
労使間・従業員間で納得できる制度にし、双方の満足度が高まる運用を目指したいものですね。