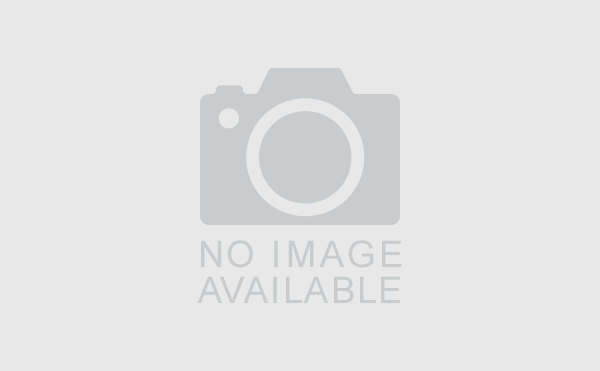懲戒処分の調査に応じない場合の対応
はじめに
従業員が何らかの事案を起こしたため、会社が調査をしようとしたところ、
調査に応じないことがしばしばあります。
今回は、そのようなケースの対応方法について述べていきます。
調査(ヒアリング)と弁明の機会は違う
多くの懲戒処分に関する規定には「弁明の機会」という文言があると思います。
しばしば「調査(ヒアリング)」と混同されることもありますが、両者の性質は異なります。
【実施の時期】
調査(ヒアリング) ➡ 懲戒処分の手続に入る前の段階
弁明の機会 ➡ 懲戒処分の手続に入った後の段階
【実施の根拠】
調査(ヒアリング) ➡ 業務命令の一環
弁明の機会 ➡ 懲戒処分の手続の一環
【実施の目的】
調査(ヒアリング) ➡ 事実関係の調査
弁明の機会 ➡ 調査結果に基づく言い分を聞く機会
このような違いがあることを念頭に置いておきましょう。
調査(ヒアリング)に応じない従業員への対応
一般的には上長などが事実関係の調査(ヒアリング)をしていくことから始まりますが、
この時点から態度を硬化させたり、調査に応じないことも実際にあります。
ここでのポイントは「この時点ではまだ懲戒処分の段階に入っていない」ということです。
つまり、この段階ではあくまでも「業務命令による調査(ヒアリング)」を実施しているということです。
これに応じないということは、事実や心証が黒に近いということが言えますので、
会社側としては淡々と次のステップ(懲戒処分)へ進むことが肝要です。
ただし、調査(ヒアリング)に応じるように働きかけることも重要です。
参考となる裁判例(ポイント抜粋)
日経クイック情報(電子メール)事件(東京地裁 2002年2月26日判決)
・企業秩序は、企業の存立と事業の円滑な運営の維持のために必要不可欠なものなので、
会社は、企業秩序を定立し維持する権限がある。
・労働者は、労働契約を締結していることによって当然に企業秩序を遵守する義務がある。
↓(したがって)
・企業は、具体的な規則を定めるまでもなく、企業秩序を維持確保するため、
具体的に労働者に指示、命令することができる。
・企業秩序に違反する行為があった場合には、その違反行為の内容、態様、程度等を明らかにして、
乱された企業秩序の回復に必要な業務上の指示、命令を発し、事実関係の調査をすることができる。
↓(ただし)
・調査や命令が、企業の円滑な運営上必要かつ合理的なものであること。
・その方法態様が、労働者の人格や自由に対する行きすぎた支配や拘束ではないこと。
↓(よって)
・本事件は、以下の事情から業務命令に違法性がない。
①30分ないし60分程度の事情聴取が2回行われたにすぎない。
②冒頭に事情聴取の趣旨を説明した上で開始している。
③質問内容等も特に不適切なものではない。
④強制にわたるものとまでは認められない。
弁明の機会に応じない従業員への対応
懲戒処分の規定で弁明の機会に応じない従業員も稀にいます。
このような場合、事実や心証が極めて黒に近いということが言えるでしょう。
当然、処分の程度を左右することになりますので、応じなかったことも加味して処分の程度を決定します。
規定に弁明の機会に応じない場合を想定した文言があるか確認しておきましょう。
おわりに
懲戒処分の規定に手続が明記されている場合、基本的には厳格に手続に則って進める必要があります。
もし手続の規定がなかったとしても、弁明の機会を付与しておくことが望ましいです。
懲戒処分に至らないように軟着陸させることが理想的ですが、やはりリスクを想定しておくことが肝要です。
調査(ヒアリング)や弁明の機会に応じないからといって保留状態が続くと、
企業秩序の乱れを加速化させることになりかねません。
自社の懲戒処分の規定に不安がある、または見直したいという場合は、当事務所へご用命ください。