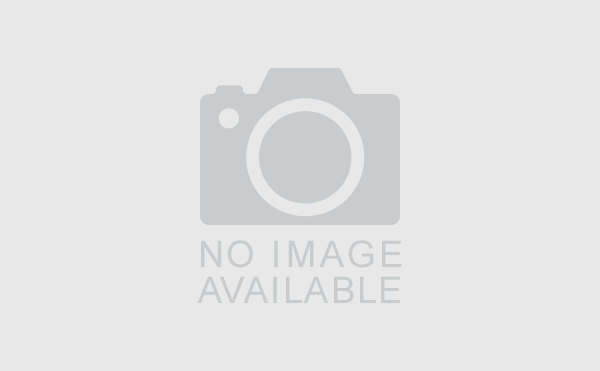安全配慮義務とは
はじめに
労務管理に携わるとよく耳にする「安全配慮義務」。
名称から何となくイメージできるものの、そのイメージは漠然としたものではないでしょうか。
今回は、そんな安全配慮義務についてのイメージが深化できる内容です。
根拠となる法律
安全配慮義務は、労働契約法第5条に使用者の義務として明文化されています。
条文:「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」
まずはこの条文のポイントとなる用語を掘り下げていきましょう。
「労働契約に伴い」
「労働契約に伴い」とは、使用者と労働者との間に労働契約関係があるという事実だけで成り立つということです。
つまり、就業規則や雇用契約書に記載がなくても、使用者には安全配慮をすることが義務付けられているといえます。
また、書面上は雇用関係がない場合でも、実態として雇用関係があるとみなされれば安全配慮義務が課されることになります。
「生命、身体等の安全」
「生命、身体等の安全」の“等”には、精神的な部分すなわち心身の安全も含まれます。
ここ2~30年で精神的部分の安全配慮に関するトラブルは飛躍的に増加しています。
怪我などとは異なり、見えにくい部分ゆえに高いリスクが潜在しているといえます。
「必要な配慮」
「必要な配慮」、これが最も知りたい部分であり、分かりにくい部分ではないでしょうか。
ヒントとなる判例(川義事件:最三小判昭59・4・10)を見てみましょう。
「安全配慮義務の具体的内容は、労働者の職種、労務内容、労務提供場所等安全配慮義務が問題となる当該具体的状況等によって異なるべきものである。」
すなわち、発生を防ぐためにどのような手段を講じるかは、事案や会社によって異なるということです。
主な事案
ではどのような事案が安全配慮義務を問われやすいのか、いくつか挙げてみたいと思います。
| 事故 | 疾病 | 熱中症 | 感染症 |
| 長時間労働 | ハラスメント | 在宅勤務 | 受動喫煙 |
| 基礎疾患を有する労働者 | 障害を有する労働者 | 外国人労働者 | 自然災害(天変地異) |
これら事案においては、安全配慮義務を念頭に置いた対応が求められるということです。
対応のポイント
安全配慮義務は「結果」ではなく、「手段」が求められます。
この手段とは、「使用者が安全と健康を確保するために十分かつ合理的な行動をしたか」ということです。
また、安全配慮義務が違反か違反ではないかは「予見可能性」と「結果回避可能性」が基準となります。
予見可能性:事故などの結果が発生する可能性を事前に予測できたかどうか。
結果回避可能性:可能性を予測できたとして、それを回避することが可能だったかどうか。
つまり、「予見可能性」と「結果回避可能性」に基づいて「手段」を講じることが求められるということです。
おわりに
安全配慮義務は、訴訟の段階に進んでしまうと使用者側に厳しい判断が下る傾向が多いです。
このような事態をできるだけ予防するには、日頃から労務管理の専門家にアドバイスを仰ぎ、対応していくことです。
当事務所では、どんなに些末だと思われることであっても全てに耳を傾け、相談者の安心・安全に尽力しております。